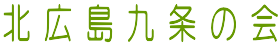2023年11月の例会に続いて星槎道都大学専任講師の後藤啓倫さんにお話を伺いました。

盧溝橋事件から始まった日中戦争は長期化して米・英・蘭との戦争につながり、日本の敗戦まで続きました。また、強制連行や南京虐殺事件、従軍慰安婦問題など外交上の争点となることも多く、現在でも記憶をめぐる問題は解決に至っていません。

盧溝橋事件は偶発的なものでした。1937年7月7日、日本軍の夜間演習中に近くの中国軍から銃声があり、日本兵1名が行方不明となりました。兵士は20分後に帰還しましたが、日中両軍の間に緊張が高まっており翌朝には軍事衝突に発展しました。現地では数日後に停戦協定が成立しましたが、日本政府は追加要求などさらなる強硬策を現場に指示しました。中国側は政府間の外交交渉で解決すべきと主張しましたが、日本政府・軍部は交渉では解決できないと判断しました。

同月末、日本軍は総攻撃を開始し全面戦争に突入しました。背景には満州事変以来の日中関係の悪化があります。日本は傀儡国家満州国を確実なものにするため、陸軍は華北分離工作を進めていました。中国側では国共内戦が続いていましたが、蒋介石は抗日よりも共産党排除を優先する「安内攘外」策を採り、ドイツからの武器供与や軍事顧問団招待など軍備の充実を図っていました。しかし、張学良が蒋介石を拘禁して一致抗日を訴えた「西安事件」を経て、第2次国共合作が始まりました。こうして中国側に準備が整ったタイミングで日中戦争は始まったのです。

当時の首相近衛文麿は、政治家が軍人に先立って国の進むべき道を示すべきという「先手論」に立っていました。しかし、政治家はいったん戦争にのめりこむと軍人より強引になる傾向があります。この政治家のリーダーシップが悪い方向に発揮されてしまいました。
1937年10月から在中国ドイツ大使トラウトマンによる日中和平工作が始まり、蒋介石は華北の主権を侵害しないことを条件に和平に応ずる構えでした。日本側も、陸軍(特に参謀本部)は対ソ戦に備えて応じようとしました。
しかし、ドイツの仲介がなくとも中国に要求を飲ませることができると考えた近衛首相は消極的で、1938年1月には政府は和平交渉を打ち切り「国民政府を対手とせず」との第1次近衛声明を発表しました。近衛首相は親日政権を樹立して、そこと和平交渉しようとしましたが、事態は想定を超えていきます。占領地域を拡大しても蒋介石は降伏せず、大義名分の乏しい戦争に日本国民のあいだにはえん戦気分が蔓延していきます。

そこで「東亜新秩序」をめざすという第2次近衛声明を発表して、それまでの強硬な対中国方針をトーンダウンさせますが、蔣介石はそれになびかず戦争は泥沼化していきました。その理由として、①中国の国力やナショナリズムを見誤っていたこと、②ソ連を警戒する陸軍が「一撃論」を背景に兵力を限定的に投入したこと、③中国軍がドイツの支援で強化されていたことなどが指摘できます。
1930年代のドイツは日本と防共協定を結ぶ一方で、中国とは通商上の友好国でした。ナチ党には日本寄りが多くとも、ドイツ外務省には中国寄りが多かったといわれています。

南京大虐殺に関しては、当時の日本政府の内部にも認識がありました。東京裁判で明らかにされましたが、記録が残っていないため犠牲者の数をめぐって様々な推計があります。最近ではその議論よりも構造的要因の研究が進んでいます。事件の要因として、①「一撃論」を背景に軍紀に問題のある臨時招集部隊を投入したこと、②戦闘の長期化で食糧補給が追い付かず、現地調達から虐殺に至ったこと、③宣戦布告のない「事変」とされたために、戦時国際法という歯止めがきかなかったことなどがあげられます。③については、アメリカの戦争状態にある国に対する武器・軍需物資の輸出を禁ずる「中立法」の適用を日中双方が避けるためでした。

日中戦争の直接のきっかけは盧溝橋事件でしたが、背景には第1次世界大戦時の「21か条要求」以来の積み重ねが遠因としてありました。長期化した日中戦争はヨーロッパ情勢と連動して日米開戦を招くこととなりました。

日中戦争には戦争の惨禍とその記憶の課題が凝集されており、事実と記憶をトータルに語り継がなければなりません。