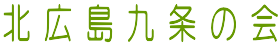63年の人生を振り返ってみて、本当に我が国史上最も良い時代を生きたと思う。
農家生まれの田舎育ち、小さかったときは貧しかった....という記憶のカケラはあるが、団塊の世代にはほぼ完全にハズれ、高度経済成長のはしりに乗って、青年時代はほどほどのゆとりある大学生活を送ることができた。
学生運動もほぼ収束し安定した社会と経済発展とともに卒業後、社会人になってからは“農”の道に入った。
当初、冷災害等でひどい痛手を被ったこともあったが、気付いてみれば40年の道のりを経ていた。その間、米余りから減反・転作が農政の柱となり、食管法撤廃、食の安心安全、多様化、栄養、グルメ、健康、環境保全、輸入自由化への動き.....食にまつわる国内外の複雑な要因にさらされ続けたが、よき家族を持ち、良き地域社会と人々に恵まれ、ほぼやりたいことをやって、さほど後悔の念もなく、現在の姿にたどり着いていたという次第。しかも、後継者に引き継ぎができるところまで来られたことは本当に喜ばしいことと思う。
先の大戦後72年が過ぎ、翻ってとりあえず安穏とした日本から目を転じ世界を見れば、紛争の惨禍が満ちあふれ、不本意に翻弄された人生を送らねばならない難民のなんと多いことか。
つらつら思うに、私が今あるのは冒頭述べたように明治以降、近代日本においては類い希なる平和と人権が尊重される時代に生まれ、生きて来られた賜物であったからと思う。私の両親、祖父母、さらにその前の時代はずっと貧乏と戦争の影が暮らしに入り込み、生きる(食べる)ことのみの生活で、“夢”ある人生を全うすることがほぼ封じられていたのではなかったか。
だが、今の世相は紛争、テロ、ミサイル攻撃など迫りくる外国からの脅威に対抗するため、自国を守るための自衛隊から同盟国とともに他国をも攻めることのできる軍隊を持てるよう改憲を前提に対策をすべしという声、70年という不戦・平和な時代は現憲法下でひたすら専守防衛のスタンスに徹してきたからという護憲の声、どちらも平和を希求していると思われるのに、真逆からのアプローチになっている。
仮にこの大きな選択をなさなければならなくなったときは、私は迷わず後者をえらぶ。子や孫たちが夢を持って生きられる社会の継続を思うとき、この70年積み上げてきた自衛隊員がただ一人として戦争や紛争で戦死していないという世界に類のない誇るべき普遍的な価値、これをもっともっと積み上げる方向で行くべきと考えるのである。
なんと現実を直視しない無責任な夢想家と思われるかもしれないけれど、現代は力による平和は世界中どこを探してもないように見える。なんといっても一番の国防力を高める方法は国民一人一人の“民度”(自立、知性、教養、品格、労働、健康、涵養、情熱.......)を高めることだと思う。軍備で全てのスキを埋めるという発想ではなく、他国には「あぁこの国民にはツケ込むスキがないだろうな」という、国民の“民力”を高めていく努力が求められるだろう。
公教育は国の専権と捉えず、画一でない、地方ファーストで地域の文化を土台にした多様性を持って民度・民力を高めること、それを束ねて現下の日本国憲法を頂けるのであれば鬼に金棒の日本ができるに違いない。
私のような農家は、時を越えて豊かな恵みをもたらす農地を後代の人々に残していかなければならないと思っている。民度を高めることを約束するのは“平和”と健康を維持できる“食べ物”にほかならないのだから。(K.T)